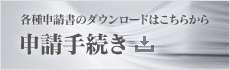洋学博覧漫筆
| ようあん |
| Vol.20 榕菴と西洋の音楽 |
|
▲榕菴の音楽関係資料 (上:津山洋学資料館所蔵、 下:早稲田大学図書館所蔵)
わたしたちの暮らしは、いろいろな音楽で満ちあふれています。津山藩の洋学者たちも音楽が好きだったようで、藩医の宇田川玄真は三味線が得意だったそうです。また、その養子となった榕菴も音楽には強い関心を持っていました。 天保元年(1830)、榕菴は33歳の夏に、同じ津山藩の藩士から中国で使われる笛の記譜法を習っています。しかし、思うように上達しなかったようで「私の感性は音律の高低には鋭くないようだ」と残念そうに書き残しています。 江戸時代の後期には、中国から伝わった明楽や清楽という音楽がはやっていました。榕菴が学んでいたのはこうした音楽で、月琴という清楽で使う楽器も好んで弾いていたことが知られています。ところが、それで終わらないのが榕菴です。演奏するだけでは飽き足らず、『清楽考』という研究原稿をまとめました。 さらに榕菴は『西洋楽律稿』などと題された数種類の原稿を書き残しています。これらの原稿を詳しく見ていくと「アルト」「バス」「メロヂー(メロディ)」「オクターフ(オクターブ)」といった言葉が登場し、わたしたちを驚かせるのです。 榕菴がいつ頃から西洋音楽に関心を持ったのか、はっきりとは分かっていません。しかし、文政9年(1826)にオランダ商館長に随行して江戸へやって来たシーボルトと面会した榕菴は、その時の印象について「シーボルトは音律を理解している」と書き残しています。何か二人で音楽の話でもしたのでしょうか。あるいは、シーボルトは江戸までピアノを持参して演奏することもあったので、榕菴にも聴かせたのかもしれません。 これまでの研究によって、榕菴の原稿は、振動や音程といった音の性質や西洋と日本の音律用語の対照などをまとめていることが明らかになっています。当時は西洋の音楽を実際に耳にする機会はほとんどなかったので、書物から得た知識で理論的な研究をしていたのでしょう。 原稿に残された音符を眺めていると、研究をする榕菴の脳裏には、もしかするとシーボルトが奏でるピアノの旋律が流れていたのかもしれない、そんなふうに思われるのです。
|
| < 前号 | 記事一覧 | 次号 > |